整理・整頓・清潔の3Sは、企業で取り入れられている生産性向上などに寄与する活動のことですが、家庭にも取り入れながら生活してみませんか?
整理と整頓。
清掃と掃除、そして清潔。
これらは、日常の中で意識せずに行っていること。
でも、本当の意味を理解して意識的には取り組んでいませんよね?
まずは、自分で3Sの意味をしっかりと理解しましょう。
そうすると、子供に対しても理論的に納得させられる片付け方法を教えることができるでしょう。
掃除のコツ先生 掃除のコツを覚えてキレイな生活

整理・整頓・清潔の3Sは、企業で取り入れられている生産性向上などに寄与する活動のことですが、家庭にも取り入れながら生活してみませんか?
整理と整頓。
清掃と掃除、そして清潔。
これらは、日常の中で意識せずに行っていること。
でも、本当の意味を理解して意識的には取り組んでいませんよね?
まずは、自分で3Sの意味をしっかりと理解しましょう。
そうすると、子供に対しても理論的に納得させられる片付け方法を教えることができるでしょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事

掃除を楽しくする方法!面倒な掃除を楽しくして部屋を掃除しよう
掃除をするのが面倒でどうしても重い腰が上がらないという人もいますよね。掃除を楽しくする方法が分か...

片付けは不要なものを捨てることから始めよう!運気も上昇します
運気を上げるためにはいらない物を捨てて片付けることが大切だと言われていますが、捨てる物の基準がわから...

毎日の掃除の仕方を解説!掃除の習慣化で綺麗な家を維持する方法
毎日の掃除を一体どのようにすれば、ずっと綺麗な家を維持することができるのか知りたい!という主婦の方も...
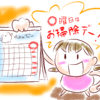
ズボラでもできる掃除術。掃除のヒントやマイルールの作り方とは
掃除は面倒、苦手、あまりしないというズボラさん。 ズボラでもできる掃除のポイントがありました。...

掃除のやる気スイッチをONにする方法!家の掃除で心もスッキリ
家を掃除しなくてはと思っていても、なかなかやる気スイッチが入らずに行動に移せないことってあります...

家の掃除が面倒だ!面倒に感じない掃除への考え方とその方法とは
家の掃除が面倒。 やらなきゃならないのに、やる気が出ない。 わかる!わかります! テスト勉...
スポンサーリンク
子供に対して「整理整頓しなさい!」とよく叱る母親の話しは耳にしますが、実際の整理と整頓の意味をみなさんは理解していますか?
そもそも整理と整頓には違う意味合いがあります。
したがって、整理整頓とは乱れた状態を整え片付け、いらないものは破棄するという意味合いがあるのだと思います。
ここまで意味が深いとはなかなか普通は考えないですよね。
言葉の意味を理解することで、より整理をしやすい環境が身につくキッカケにもなりますので、よかったら頭の隅にでも保存しておいて下さい。
日常の生活の中で大切なのが、整頓の作業だと思います。
そして、断捨離(普段使ってないけどいつか使うかも知れないからなかなか捨てられなかったものを捨てる作業)することで整理完了という流れになるのではないでしょうか?
整頓しておくことで、整理しやすい環境が作られているわけですから、より少ない時間で整理ができますよね?
まとめて1日がかりで整理整頓をこなすより、毎日5分10分かけて整頓しておくことでより効率の良い作業ができるといえるのだと思います。
では、もっと深く掘り下げていきましょう。
次は「清掃と掃除」です。
確かに、身近に言葉として発するのは「掃除しなさい」ですよね?
ただ、業者さんが来ておこなってもらう作業は清掃だったり、書面で記入する時も清掃と記入することが多いようにも思います。
実は、清掃と掃除にもそれぞれ意味があったのです。
とされています。
微妙に違いますね。
では、掃除してから清掃しなさい、という流れになるようですね。
やはり用途が違う見解で、掃除とは拭いたり掃いたり汚れを取り除く作業という意味に比べ清掃とは汚れを取り除くだけではなく、普段気づかないような部分の細部にまで手をかけ清潔な環境を整えるという意味が含まれているのです。
ということは、掃除より、より丁寧な作業が清掃といえるのでしょう。
では、先程の文章の途中にでてきた「清潔」とはどのような意味合いがあるのでしょうか?
この際なので、しっかり調べたいと思います。
と記載されていました。
思ったとおりの意味でしたが、正確に調べることで更に意味合いが深くあることを知りますよね。
では上記の整理・整頓・清潔を家庭にも取り入れるためにどのような事に気をつけたら良いのでしょうか?
検証してみましたので、紹介したいと思います。
子供は親を見て育つと言われるほど家庭環境が性格にも影響してきます。
逆を言えば、子供を見てたら親の感じがわかるとも言われる位、日々の環境は成長する上でとても重要なことなのです。
では、子供にどのように接することで上手く伝わるでしょうか?
基本的には、怒る・叱るという事は最後におこします。
最初は納得してくれるよう、話しかける事から初めて毎日行することが必要なんだという事をわかってもらうという事を気をつけていれば、例え片付けに時間がかかる子供でも意味合いは理解してくれると思うのです。
最後になりましたが、5Sと言われている中の最後の躾(しつけ)についてすこしお話ししたいと思います。
●躾(しつけ)
一般的に、礼儀・作法を教え込むこと。
この躾も実は整理整頓する上でとても大切な心構えなのです。
例えば、人の家にお邪魔した時、靴をバラバラに散らかした状態で家の中に入ったとします。その見た目は、整頓されていない、清潔とは言えない状態ですよね。
こういうことからも5Sの中の1つとも言われているのでしょう。
色々な親もいる通り、色々な家庭環境があります。
私自身、過度な躾は必要ないと思いますが、最低限の整理整頓に繋がる躾はあったほうが良いのかなとも感じます。
過度な躾をすることで、子供の将来に悪影響を及ぼし、萎縮させてしまうということも十分考えられます。
最低限必要な脱いだものは片付ける、使ったものは片付けるなどの作業をキチンと教えておくことは忘れず実践するべきかとは思います。