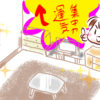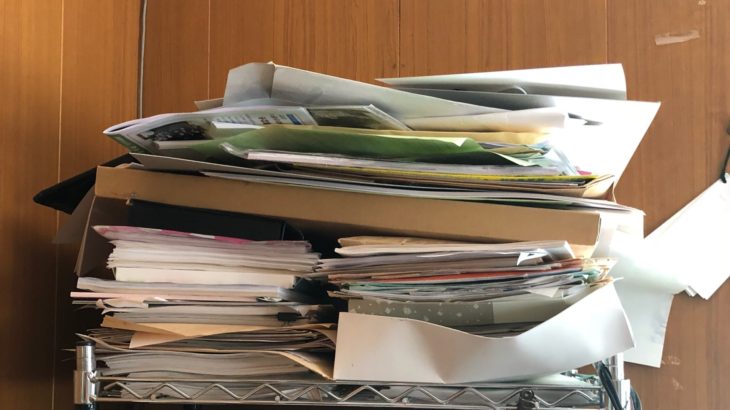子供が掃除をしないとイライラしても、子供が掃除をするようにはなりません。
『掃除』や『片付け』という単語は知っていても、具体的に何をどうすることが『掃除』や『片付け』なのかを子供は知りません。
そう、中学生や高校生でも、掃除や片付けのノウハウを持っていないのです。
よく考えてください。
ママはどうですか?
雑誌に出てくるような、整理整頓収納されているキッチンでお料理を作っていますか?
冷蔵庫の中身はどうですか?
頻繁に開けない扉の中は、どのような状態ですか?
そう、子供には『掃除』や『片付け』のノウハウがないのです。
ですから、始めに子供の部屋を一緒に片付けることから始めてみてください。
整理整頓された空間を作ってから、一緒に掃除をしてくださいね。
『掃除しなさい』
『片付けなさい』
と言うだけでは意味がありません。
一緒に、片付けや掃除をして、子供にノウハウを教えていきましょう。
関連のおすすめ記事
子供が部屋の掃除をしなくてイライラする。どうして掃除をしないのか
子供の部屋がいつも散らかっていて、口うるさく「片付けなさい」と言っても片付けがなかなか進まないと、イライラしてしまうということはありませんか?
脱ぎ散らかしたままの服や、遊び終わったおもちゃがあちこちに残ったまま、何とも思わないわが子を見ると、「どうしてこの子は片付けができないんだろう」と怒りよりも心配になってしまうこともあるかもしれませんね。
周りのお友達を見て、きれいに片付けているのを見たらなおさら不安になってしまうことも。
でも、重要なのはもっと根本的なことということに気づきましょう。
親が言う「片付け」と子供が思う「片付け」の意味合いは違うことも
お子さんが片付けができないのは、できないのではなく、片付けの仕方が分からないことが原因という可能性も大いにあります。
自分自身を振り返ってみよう
自分が子供だった時を思い出してみましょう。
誰に教わらなくても片付けが自然に出来る子供でしたか?誰でも、どこかで片付けの仕方を教えてもらっているはずです。
子供は親の背中を見て育つと言いますよね。
親が日頃から部屋の整理整頓をして、快適な空間にしていれば、子供も自分から身の周りを片付けるようになります。
逆に物がいつも出しっぱなしだったりする部屋で暮らしていると、その状況が日常なので、自分の部屋が散らかっていても気にならなくなります。
「片付けをしなさい」と子供に全責任を押し付けるのではなく、「一緒に片付けしようね」「部屋がキレイになると気持ちがいいね」と子供と一緒になって片付けをしながら、片付けの仕方を教えるということが大切です。
『掃除』と『片付け』について
「掃除」と「片付け」という2つの言葉は、部屋をキレイにするという意味では同じ内容の言葉にも思えますが、実は意味合いがまったく違う言葉です。
片付けをキープすることが掃除の効率をアップさせる
「片付け」は、散乱している物を元の場所に戻してキレイにすることで、「掃除」は、汚れを取り除き、キレイにすることです。
キレイにするというゴールは同じでも、道順が違うのです。
片付けをしていない状態で掃除しても作業の効率が悪いだけです
部屋の汚れやホコリを取り除き、キレイにするためには、しっかりと「片付け」られていることが前提です。
そのため、日頃から正しい方法で片付けられているということがとても重要です。
きちんと片付けられている部屋では、いつでも掃除に取り掛かれるからです。
掃除のために一時的に物を避けてもその場しのぎにすぎず、本当の意味での「片付け」にはなりません。
物の定位置を決め、その場所に適切にしまうことが正しい「片付け」です。
子供が掃除をしないのは、掃除や片付けがどういうものか知らないから
片付けをしない子供に悩んでいる人は、自分の今の状態を考えてみましょう。
「冷蔵庫の要らない物を整理しないと…」「あの引き出しも整理してキレイにしなきゃ…」など、日々整理整頓することに頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。
子供に片付けや掃除をするメリットを教える
掃除や片付けは、大人になっても習慣として身に付けるべきものですよね。
掃除や片付けの習慣がなければ、あっという間にゴミ屋敷になってしまう可能性もあります。
子供にも、自分の部屋は自分で整理する習慣を身に付けさせたいという気持ちはとてもよく分かります。
でも、子供は大人と違い、掃除や片付けの意味が分かっていないことが多いのです。
大人であれば、片付けや掃除をちゃんとしなければ、部屋が汚れて、カビやホコリが増えて健康にも影響が及ぶなど考えますが、子供は片付けや掃除にそこまでの必要性を感じていません。
なぜなら、片付けや掃除をしなくても困ることがないから。
子供にとって、片付けは、親に言われて仕方なくする面倒なお手伝いです
子供に片付けをやる気にさせるためには、片付けをすることによってどんなメリットがあるのかを実感させることも大切です。
ひとつの方法として子供部屋を子供が好むインテリアに模様替えすることもおすすめです。
好きなキャラクターのカーペットや時計などを揃えたり、おもちゃを種類別に仕分ける収納グッズも遊び心を加えて、シールなどでアレンジしてみましょう。
なんとなく自分の部屋だった居場所が、家の中でも大好きな場所に変われば、率先して片付けするようになるかもしれません。
掃除の前に、まずは片付け。子供と一緒に整理整頓してみましょう。しないのではなく、知らないのです
子供に、おもちゃが散乱して汚い部屋を片付けるように言っても、乗り気のない返事や遊びに夢中になって片付けが進まず、言った自分がイライラしてしまうことありませんか?
そんな時は、子供の気持ちに立って考えてみることが大切です。
子供と一緒に考えながら、物の量を減らそう
子供からしてみると、今夢中になっている遊びを中断してまでしなきゃいけない片付けは、2つ返事で素直に取り組めるような物でしょうか。
答えは、言うまでもなく逆ですよね。
せっかく自分の周りに出したおもちゃがたくさんあるのに、どうして片付けなきゃいけないのか、理由がわからないので、理不尽にも思えるでしょう。
そもそも、片付けが出来ないのは片付けの仕方がわからないということもあります。
これでは、いくら「片付けなさい」と言われたところで、わからないので、出来るはずがありませんよね。
片付けしなさいというよりも親が一緒になって行い、片付けをすることの楽しさを感じさせましょう
物が多すぎると、片付けも掃除も効率が悪くなります。
増えがちなおもちゃは、子供の気持ちを優先しながら、壊れていたり、使わなくなった物は、処分したり、人に譲るなどして量をへらすことも大切です。
モノの位置をしっかり決める。位置が決まらないものは不要なもの
部屋の中に、いつのまにか物が散乱してしまうのはなぜでしょう。
大きな理由としては、物を使い終わった後に元の場所に戻していないことです。
物の定位置は家族間で共有し子供に覚えさせましょう
物の定位置をしっかりと決めていない場合、物をしまう場所がないので、なんとなくテーブルの上などに置くことになります。
そうしているうちに、どんどん物の量が増え、散らかってしまうのです。
片付けの基本は、「モノの位置を決める」ことです。
家族がいる場合は、自分だけではなく、他の家族にもしっかりモノの定位置を共有することが大切です。
自分だけがしまう場所を知っていても、他の家族が知らなければ部屋は必然的に散らかってしまいます。
子供も使うものなら、子供がしまいやすい場所にしましょう
もし、しまう場所に悩むようなモノなら、実は必要がないモノである可能性も高いです。
モノを整理整頓しながら、家族でモノの定位置を共有し、キレイな部屋で快適に暮らしたいですね。