まな板の漂白って、どのくらいの頻度で行えばよいのでしょうか?
プラスチック製のまな板なら、塩素系漂白剤で漂白し、汚れや菌をキレイにすることができます。
ですが、木製のまな板なら、漂白剤を使うことはできません。
今回は、まな板に潜む菌。
それらをしっかりと除去し、キレイでスッキリしたまな板に保つ方法やコツについてご紹介いたします。
掃除のコツ先生 掃除のコツを覚えてキレイな生活

まな板の漂白って、どのくらいの頻度で行えばよいのでしょうか?
プラスチック製のまな板なら、塩素系漂白剤で漂白し、汚れや菌をキレイにすることができます。
ですが、木製のまな板なら、漂白剤を使うことはできません。
今回は、まな板に潜む菌。
それらをしっかりと除去し、キレイでスッキリしたまな板に保つ方法やコツについてご紹介いたします。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
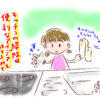
キッチン掃除に使う洗剤の種類と効果、そして掃除方法を徹底解説
キッチンの掃除を始めようと思っても、どんな洗剤を使えばよりきれいになるのか悩んでしまう人も多いのでは...

シンクのつまりを解消させたい!自分でできることとできないこと
シンクがつまった!? シンクの流れが悪い、悪臭がすると感じたら、一番に考えられるのは『油汚れ』です...

シンクの詰まりを解消したい!排水口が詰まる原因と対策・予防法
シンクの排水口が詰まってしまうと、水が流れなくなって困ってしまうものです。どうにかして詰まりを解消し...

台所掃除に重曹とクエン酸を使ったナチュラルクリーニングのコツ
台所の汚れにはいろいろなものがありますよね。 キッチンのシンクの汚れを始め、排水口の汚れや臭い、 ...
スポンサーリンク
料理の度に使うまな板は、長く使っていると色がついてしまいますよね。
すると、菌が気になるようになります。
まな板はきちんと除菌していないと、雑菌が繁殖してしまいます。
繁殖すると食中毒を起こす原因にもなりますから注意しましょう。
繁殖すると食中毒を起こす細菌には、サルモネラ菌、O157・O111などの腸管出血性大腸菌、黄色ブドウ球菌があります。
どれも名前を聞いたことがあるのではないでしょうか?
食中毒にかかった人は誰もが「辛い!もう二度と嫌だ!」と、口を揃えて言います。
まな板や包丁など直接食品に触れる物はしっかりと除菌して、清潔な状態で使うようにしましょう。
プラスチック性のまな板を使っているご家庭は多いですよね。
木のまな板に比べると軽量で安価ですから、とても使いやすいのがメリットです。
プラスチックのまな板でも、白いタイプを使われている方が多いと思います。
真っ白だったまな板は、時間が経つにつれて黄ばんでいませんか?
プラスチックのまな板は、包丁を使う度に細かな傷が出来ます。
その傷に菌が付着して繁殖すると、黄ばみとなって現れてきます。
まな板が黄ばんでいるなら、漂白するのがおすすめです。
キッチン用の塩素系漂白剤を使いましょう。
いろいろなメーカーから商品が出ていますので、自分の使いやすいもので構いません。
注意したいのは「キッチン用」を選ぶことです。
衣類用のものには界面活性剤が入っているので、まな板には向きません。
まな板の漂白頻度は、まな板の状態や使用頻度などにより異なります。
間隔が長くなると汚れも落ちにくくなりますから、1~2週間程度を目安にしてみましょう。
汚れが酷いときや、食中毒などが気になる季節には、短い間隔に調整してくださいね。
また、ノロウィルス対策としも漂白は有効です。
ノロウィルスはアルコール除菌が効かないので、これが流行っているときには細やかに行うのがおすすめです。
長く使っていて、漂白しても直ぐに黄ばんでしまうようなら買い替え時期かもしれませんね。
まな板の除菌方法は、漂白剤だけではありません。
昔から使われる除菌方法の一つに、「熱湯消毒」がありますよね。
熱湯消毒はあらゆるものの消毒に使える手軽な方法です。
強い薬剤は苦手という方でも安心して行えます。
まな板を熱湯消毒する時のポイントは、まな板を綺麗に洗ってから行うことです。
洗わずに最初から熱湯をかけてしまうと、肉や魚に含まれるタンパク質が固まってしまい、汚れが落ちにくくなってしまうのです。
ですから、必ずしっかりと汚れを落としてから、熱湯を全体にかけ流しましょう。
そして、しっかりと乾かすことも重要です。
高温多湿は、菌が好む環境です。
しっかりと水気を拭き取り乾燥させることは、カビ細菌の繁殖を防ぐことに繋がります。
プラスチックのまな板は手軽ですが、「うちでは木製のまな板を使っている」というご家庭もありますよね?
木製のまな板は、木目が美しく手に馴染みやすいですし、独特の優しい雰囲気もありますから、一度使うとプラスチックには戻れないという方も多いです。
しかし、木製のまな板はプラスチックのまな板よりもお手入れは大変になります。
まず、木製のまな板では漂白剤を使うことが出来ません。
木が変質してしまう可能性があるからです。
基本的なお手入れは、流水をまな板にあて、木目に沿ってたわしでゴシゴシとこすり洗いします。
水が溜まりやすい部分や傷になっている部分には雑菌も繁殖しやすいので丁寧に洗いましょう。
洗い終わったらしっかりと水気を拭き取って乾かします。
除菌するときには、重曹を使ってみてください。
まな板全体に重曹を振りかけて、木目に沿ってたわしで擦って洗い流します。
重曹が細かい傷に入り込み、細かな汚れも落としてくれます。
綺麗に洗った後には、酢やクエン酸水をスプレーするのがおすすめです。
除菌効果が高まります。
傷が深く内部までカビや菌が及んでしまった場合には、カンナや紙やすりを使って削り落としましょう。
この方法は木製のまな板だからこそ出来る方法なので、木製まな板のメリットでもありますね。
まな板を手軽に清潔に保ちたいなら、アルコールスプレーがおすすめです。
アルコールスプレーはプラスチックまな板だけではなく、木製のまな板でも使うことができますよ。
まずは、まな板をしっかりと洗って水気を拭き取りましょう。
それから、シューッとまな板全体に隈なくアルコールスプレーを吹きかけます。
水分が残っていると除菌効果が薄れてしまうので注意してくださいね。
アルコールスプレーを吹きかけた後はそのまま放置します。
水洗いは必要無く、乾燥したら使うことが出来ますよ。
直ぐに使いたい場合には、清潔なふきんでサッと拭いてくださいね。
アルコールスプレーはまな板だけではなく、包丁やふきん、冷蔵庫やシンクなどいろいろなところの除菌に使えるので、一つあるととても重宝します。
まな板は直接食品が触れる場所ですから、しっかりと除菌して食中毒を防ぎましょう。