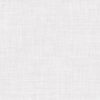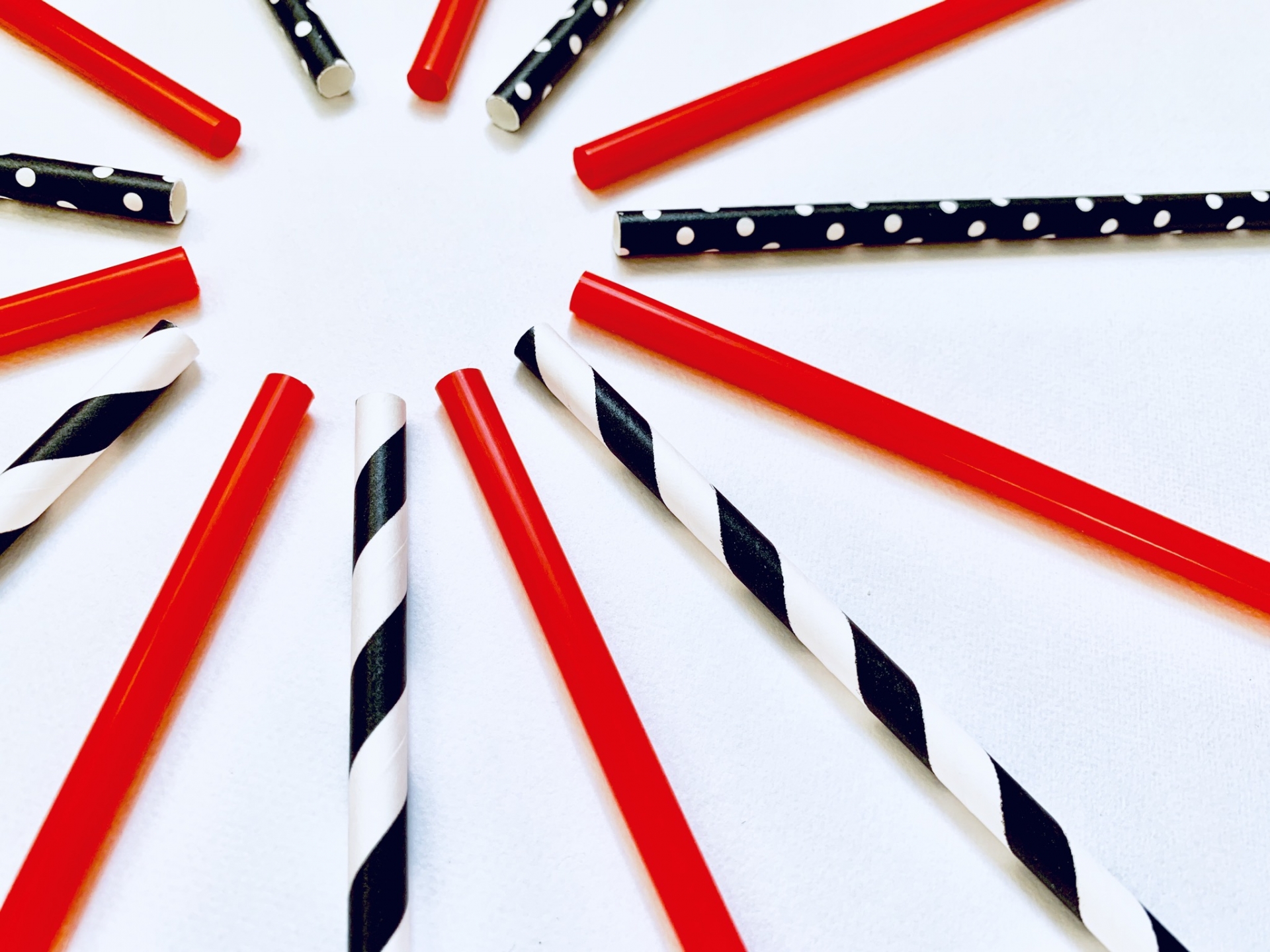自転車を処分したい!できれば無料で。
自転車を処分するのに、お金を掛けたくない場合、
1,リサイクルショップへ持っていく
2,友達などへ譲る(お下がり)
の二つが『無料で処分』の王道ですよね。
でも、あなたの自転車には『防犯登録』がされているはずです。
リサイクルショップへ持ち込む場合も、友達に譲る場合にも、自分で防犯登録の抹消手続きをしなければなりません。
この、『防犯登録』の手続きについては、各都道府県によって、ルールが異なります。
ほとんどの場合、防犯登録の抹消手続きについては無料となっていますが、手間がかかります。
ですから、100%無料で処分できるかどうかは、持っている自転車と住んでいる地区次第となります。
それでは、シチュエーション別に、自転車を無料で処分する方法を見てみましょう。
関連のおすすめ記事
自転車の処分を無料でしたいなら『リサイクルショップ』へ
自転車に限らず、要らなくなったものをリサイクルショップに持ち込むのなら、出来るだけキレイな状態にしておくことをオススメします。無料で処分するどころか、状態によってはそれだけ高値で買い取ってもらえる可能性もあるので、ここは手間を惜しんではいけません。
とくに子供の自転車は成長するごとに買い替えが必要なので、リサイクルショップでも高い需要があります。乗り方によっては部品が破損していたり、シール跡などでベタついていることもあるかもしれませんが、リサイクルショップに持ち込む前に、修理出来る箇所は直し、サビや汚れも可能な限りキレイにしておきましょう。
具体的なチェック項目はこちらです。
パンクしていないか・ライトは点灯するか・ペダルをスムーズに漕げるか・ブレーキ音はしないか・チェーンのたるみやきしみはないか・ベルは鳴るか・サビや汚れはないか
修理が必要な箇所にお金をかけたくないという方は、確かにそのままでも買い取ってもらえるかもしれませんが、当然その分だけ買取価格は低くなります。なにより、大事にしてきた自転車に対して、可能な限り新品に近い状態で手放したほうが、スッキリとした気持ちでサヨナラ出来るのではないでしょうか?
自転車をどのような形でも処分するのなら『防犯登録』の抹消手続きを必ず行うように
新たに自転車を購入した際には、販売店側で防犯登録の手続きを行ってくれますが、自転車を処分する際には、必ず自分で防犯登録の抹消手続きを行う必要があります。防犯登録の名義は変更出来ないので、自転車を処分する前に防犯登録を抹消しておかなければなりません。
防犯登録の抹消手続きは、ほとんどの都道府県で無料で行うことが出来ますが、防犯登録は各都道府県ごとに登録されているので、自転車を処分する場合だけでなく、他の都道府県に引っ越す際にも、一度現在の登録を抹消してから、新たに引越し先の住所で登録し直すことになります。
【防犯登録の抹消手続きに必要なもの】
- 自転車防犯登録カード
- 身分証明証
- 防犯登録済みの自転車
この手続自体は、自転車を購入した販売店か、それ以外の自転車販売店でも行うことが可能ですが、警察署やお近くの交番でも直接手続きすることが出来ます。一部の都道府県では警察署では登録を抹消出来ない場合もあります。さらに、防犯登録を行った本人(所有者)以外は登録を抹消出来ない場合もありますので、事前に確認するようにしましょう。
自転車の処分を無料でしたいなら、友達に『お下がり』
いらなくなった自転車を無料で処分したいのであれば、友達などに譲るのが一番手っ取り早い方法です。
大事に乗っていた自転車に見ず知らずの人が乗るよりは、知っている人にお下がりとして乗ってもらったほうが嬉しいと思う人も多いのではないでしょうか?
ただし、この場合も事前に自転車の防犯登録を抹消しておく必要があります。いちいち手続きが面倒だからとそのまま譲ってしまうと、何らかの事情で警察が防犯登録の照会をした際に、元の所有者とは別の人が乗っていることで、盗難した自転車だと誤解されてしまう恐れもありますので、たとえ近しい友達であっても忘れずに手続きしておきましょう。
自転車防犯登録カードには、以下の情報が記載されています。
- 所有者の名前
- 住所
- 電話番号
- 防犯登録番号
- 車体番号
もしも防犯登録カードを紛失してしまった場合には、自転車の保証書もしくは車体番号が記載されている領収書などを持参して、自転車の所有者であることを証明する必要がありますので、まずは防犯登録カードが手元にあるかどうかを確認しましょう。
のちに新しい所有者が再登録する際には、数百円の手数料がかかります。最寄りの自転車販売店で手続きを行ってください。ただし、自転車の防犯登録の有効期限は、登録した翌年から10年間に限られますので、購入から10年以上が経過している場合は、登録抹消の手続きを行う必要はありません。
自転車をお下がりするなら『譲渡証明書』をつけて渡そう
お下がりとして自転車を処分する際には、防犯登録を変更する必要があります。先ほど、自転車の防犯登録を抹消する際に防犯登録カードを紛失していた場合は、自転車の保証書等を持参する方法をご紹介しましたが、引っ越しや片付けの際にそれらも一緒に紛失してしまっている可能性がありますよね。その場合は、元の所有者が新しい所有者に対しての譲渡証明書を書いてあげるという方法もあります。
わかりやすく言うと、「私はたしかにこの人(新しい所有者)に自転車をあげました」ということを、書面で証明してあげるということです。譲渡証明書に関しては、とくに決まった書式はありませんが、インターネット上にある譲渡証明書のサンプルをダウンロードして使用することも出来ます。
自転車を買い換えるなら無料で処分してもらえることも
新たにクルマを購入する際には、古いクルマを下取りに出すこともありますよね。状態によっては引取手数料がかかる場合もありますが、たとえ査定価格がつかなくても、まだ乗れる状態であれば無料で引き取ってもらえることもあります。
自転車に関しても同様に、自転車を買い換える際には古い自転車を無料で処分してもらえる場合があります。店舗によっては有料となることもありますが、多くの販売店でこのサービスが実施されていますので、それぞれの購入先で確認してみてください。
いくら自転車を処分するのにお金をかけたくないからといっても、不法投棄するのは絶対にやめましょう。車体番号を見れば所有者はわかってしまうので、登録抹消の手続きをしたうえで、適切な方法で処分するようにしてくださいね。